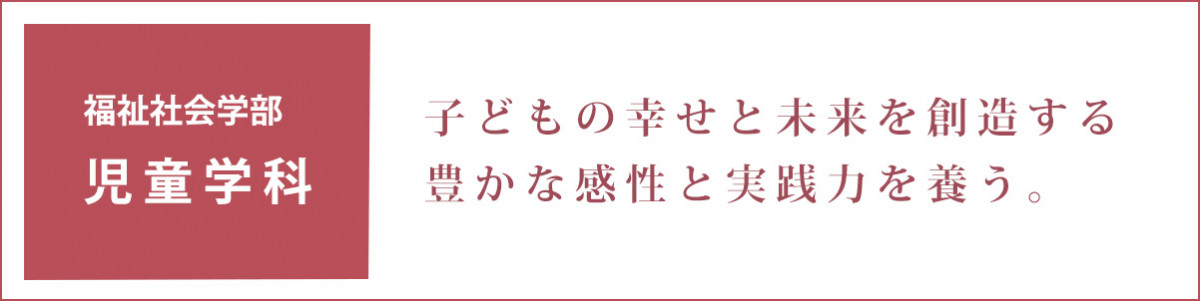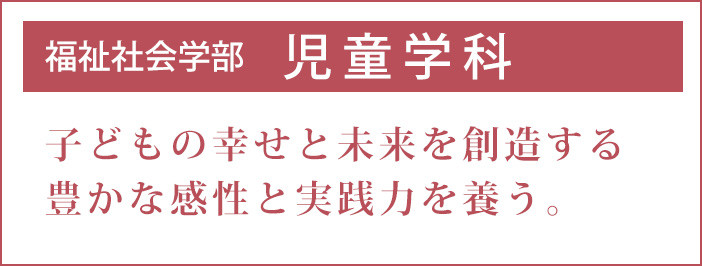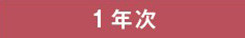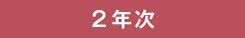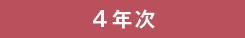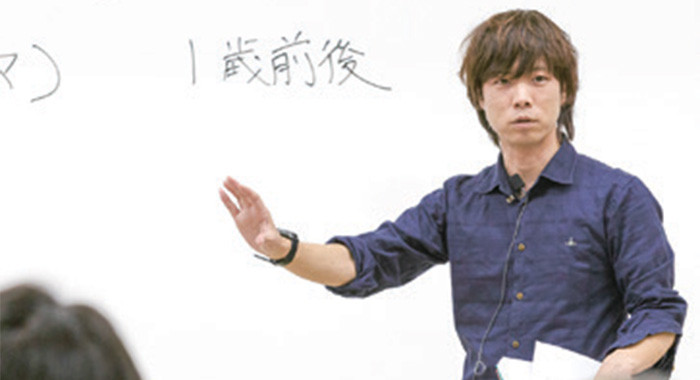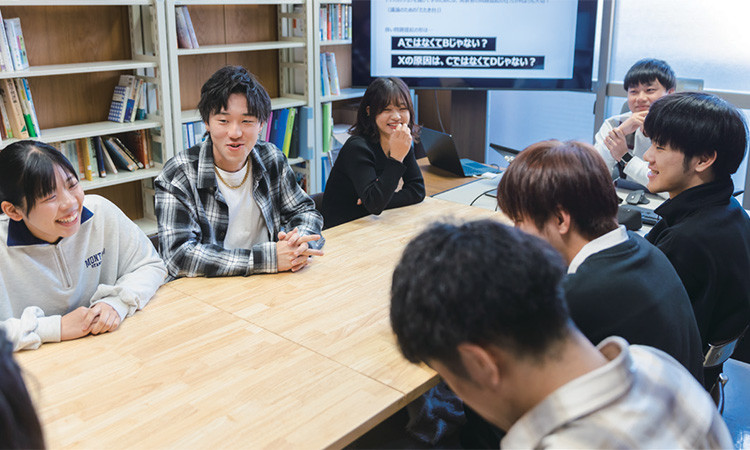STUDENT'S VOICE
4 年 脇元 朔太郎さん( 熊本県・八代高等学校出身)
私は小学校教員になるために、教育現場の現状について重点的に学びたいと思い本学を志望しました。授業では、小学校・幼稚園・保育園の内容をそれぞれ専門の教員が指導してくださるため、教育現場の現状や子どもとの関わり方を学べるほか、体験的な活動を通して理解を深めることができています。
児童学科で学ぶこと
教育・保育の現場に留まらず、現代の子どもたちを取り巻くあらゆる諸問題を真摯に考え、教育と福祉の両側面から「子ども学」を学びます。2 年次以降、福祉科目に重きを置いた「保育系コース」と教育科目に重きを置いた「児童教育系コース」に分かれて学んでいきますが、全学科生が「小学校教諭」「幼稚園教諭」「保育士」の3 つの免許・資格を同時取得可能なカリキュラムです。これらに加えて、2026 年度入学生からは、日本アタッチメント育児協会が認定する「育児セラピスト1級資格( 申請中)」及び「ABM アタッチメント・ベビーマッサージインストラクター資格(申請中)」の取得も可能となる予定です(九州の大学・短大では初の認定校となる見込みです)。
めざせる免許・資格
| ● 小学校教諭一種免許状 | ● 司書教諭 |
| ● 幼稚園教諭一種免許状 | NEW! 育児セラピスト1級(申請中) |
| ● 保育士 | NEW! ABMアタッチメント・ベビーマッサージ インストラクター( 申請中) |
| ● 司書 |
学びのポイント
1 年次
児童学の基礎を学ぶ
児童学の基本的な理論や子ども理解の基礎を学びます。「保育の心理学」「教育心理学」などを通じて、子どもの成長や発達を理論的に理解し、「教育原理」や「保育原理」により、教育・保育の基礎を身につけることができます。
1 年次
児童学の基礎を学ぶ
児童学の基本的な理論や子ども理解の基礎を学びます。「保育の心理学」「教育心理学」などを通じて、子どもの成長や発達を理論的に理解し、「教育原理」や「保育原理」により、教育・保育の基礎を身につけることができます。
1 年次
児童学の基礎を学ぶ
児童学の基本的な理論や子ども理解の基礎を学びます。「保育の心理学」「教育心理学」などを通じて、子どもの成長や発達を理論的に理解し、「教育原理」や「保育原理」により、教育・保育の基礎を身につけることができます。
1 年次
児童学の基礎を学ぶ
児童学の基本的な理論や子ども理解の基礎を学びます。「保育の心理学」「教育心理学」などを通じて、子どもの成長や発達を理論的に理解し、「教育原理」や「保育原理」により、教育・保育の基礎を身につけることができます。
・児童教育系コース
いずれかを選択
どちらのコースでも「小学校教諭一種免許状」「幼稚園教諭一種免許状」「保育士資格」の3 つの免許・資格を同時に取得することができます。
※ ただし、選んだコースによって、4 年次の教育実習の校種( 幼稚園で実習を行うか、小学校で実習を行うか)が変わってきます。
経験と成長に、熱を。
フィールドワーク活動
鹿児島国際大学附属鹿児島幼稚園での見学会開催
1年次科目「新入生ゼミナール」の一環として、鹿児島国際大学附属鹿児島幼稚園の見学会を実施しました。園長先生や主任の先生から実践的な話を伺い、子どもたちの活動や帰りの会の様子を見学。子どもたちが行う手遊び等では一緒に動きを行ったり、降園のお手伝いをしたり、様々に触れ合う様子が見られました。これから保育者・教育者を目指す学生にとって、大事なモチベーションになりました。
CLOSE UP! クローズアップ授業
幼児と言葉
領域「言葉」の示す意義や機能の理解をテーマに、「絵本」「紙芝居」などの児童文化財や、言葉に対する感覚を豊かにする実践について学びます。「なぞなぞ」「しりとり」等の言葉遊びやICT を活用し、言葉の発達や重要性について理解を深めます。
■ Q&A
Q.小学校教諭、幼稚園教諭、保育士の3 つの免許・資格取得を目指す場合、実習はどのように進められますか?
A.本学科では3 年次に保育実習( 2 週間× 3 回) を、4年次に教育実習( 3 週間) を行います。その前に、2 年次に本学科独自の「基礎実習」「保育基礎実習」という科目を履修し、附属園での1 日体験実習など、段階を踏まえて実習に臨む力を身につけています。
Q.四年制大学で教員免許や保育士資格を取得するメリットは何ですか?
A.大学ならではのゆとりあるカリキュラムの中で、追加の資格取得を目指したり、多様なフィールドワーク活動や自主研究に取り組めます。2025 年3月には、鹿児島市教育委員会との連携協定が締結され、近隣の公立小学校と連携したカリキュラムの充実も図られています。
ゼミ紹介
つながりを目指す音楽と音楽活動の研究 ―子どもの発達をとらえながら―【 中村ゼミ】
福祉社会学部 児童学科
音楽を探求しつつ人として豊かな成長を目指す
幼稚園や保育園でのコンサートや、小学校や発達支援事業所での交流授業・音あそびといった音楽活動を主体とするゼミです。計画や準備、練習のほか、活動後は振り返りを行い、気づいたことや考えたことを深めます。音楽の得手不得手に関係なく参加でき、学生たちは表現力やコミュニケーション力を身につけるほか、バランス感覚を養っています。ゼミ卒業生とのつながりは強く、就職のことなど現役生にさまざまなヒントを与えてくれます。
STUDENT’S VOICE
鹿児島幼稚園でのお誕生日コンサートの実施や練習を主体としたゼミです。子どもたちとの関わり方や音楽の楽しさや面白さを感じることができました。加えてゼミ長を務めたことで自分に自信がもてるようになりました。
4 年 諏訪 加穏さん (伊集院高等学校出身)
子どもと体育・スポーツに関する総合的研究【 加藤ゼミ】
福祉社会学部 児童学科
体育のあたり前を疑い自分の興味・関心をとことん追求する
体育の授業づくりや体育嫌い、体育やスポーツにおけるいじめや差別、ジェンダー不平等、障害とスポーツなど、各学生がそれぞれ興味のある事柄を調べて発表します。そして、研究室の机を囲み、互いの目を合わせながらディスカッションを重ねます。大切にしているのはこれまでのあたり前を疑うこと。ほかにも、県内外の小中学校に赴いて体育の授業を参観したり、運動遊びの研修会を受講したりして、求められる指導技術や理論を学びます。
STUDENT’S VOICE
体育が好きだったことから本ゼミを選択。ディスカッションを通じ、自分の意見を言うだけでなく、人の意見も聞き、考えを深める経験をしました。苦手だった人前で話すことも少し克服できました。
4 年 山口 すずなさん (加世田高等学校出身)
| ■ 岩井 浩英 教授 | 教育・福祉と子どものウェルビーイング |
| ■ ⻆野 雅彦 教授 | 保育・幼児教育の原理とカリキュラム |
| ■ 加藤 凌 講師 | 子どもと体育・スポーツに関する総合的研究 |
| ■ 佐藤 慶治 准教授 | 子どもカルチャー、保育・教育における音楽コンテンツ |
| ■ 鮫島 準一 特任准教授 | 小学校理科教育の理論的・実践的研究 |
| ■ 階戸 陽太 教授 | 小学校英語教育(外国語活動・外国語科)の理論的・実践的研究 |
| ■ 関山 均 特任准教授 |
幼児造形・図画工作科教育の理論的・実践的研究 |
| ■ 帖佐 尚人 教授 | 子どもの健全育成についての総合的研究 |
| ■ 辻 慎一郎 准教授 | 教育の情報化における学習指導、教育課程等に関する研究 |
| ■ 中村 ますみ 教授 | つながりを目指す音楽と音楽活動の研究ー子どもの発達をとらえながらー |
| ■ 福島 豪 准教授 | 子どもを育てる実践的指導力の研究 |
| ■ 丸田 愛子 准教授 | 生活と遊びに関する保育実践研究 |
| ■ 吉留 久晴 教授 | 教育・学校問題の探究 |
| ■ 脇 正一 特任准教授 | 社会科教育における学習指導、教育課程等に関する研究 |