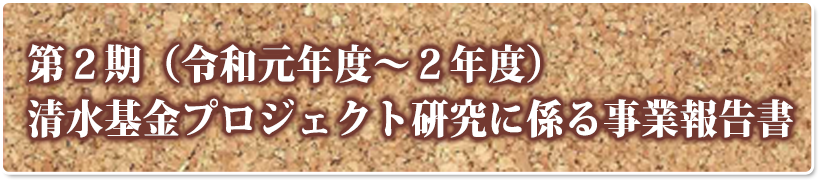第2期(2019-2020年度)研究者及び研究内容
| 研究者 | 所属 | 研究サブテーマ |
|---|---|---|
| 武田篤志 | 経済学部経営学科准教授 | 鹿児島における場所活性化デザイン研究 |
| 森勝彦 | 国際文化学部国際文化学科教授 | 香港、台湾の歴史的港湾空間の保存、再生と地域社会 |
| 高橋信行 | 福祉社会学部社会福祉学科教授 | 離島の地域福祉推進と日常生活圏域での包括ケアの構築 |
| 馬頭忠治 | 経済学部経営学科教授 | 地域と学校の境界を越えた学習環境の創出とコミュニティ・リノベーションの可能性 |
| 渡辺克司 | 経済学部経済学科教授 | 過疎・離島地域における「限界集落」問題と地域農業振興策 ー離島・過疎農村社会維持・存続・発展条件の解明ー |
| 祖慶壽子 | 国際文化学部国際文化学科教授 | 甑島における方言研究の成果を地域振興に活かす |
| 高橋信行 | 福祉社会学部社会福祉学科教授、 鹿児島県介護福祉士会 |
現代社会における福祉課題についての研究 |
| 竹安栄子 | 京都女子大学特命副学長 地域連携研究センター長 |
中国社会に関する研究(清水理論の検証と発展) 地域社会と地域振興に関する実証研究 |
令和2年度清水基金プロジェクト研究に係る事業計画書
事業計画
1.社会学的な集団論や家族論及び地域社会論又は清水盛光氏の著作に関連した研究

研究テーマ鹿児島における場所活性化デザイン研究
第一に、従来の社会学(地域社会学)が前提としてきた地域、社会、コミュニティといった概念を反省的・批判的に見直し、ホスピタリティとサービス、移動性、時間性、プライベートとパブリックをキーワードにして場所の活性化に関する理論研究をおこなう。そのさい、県内外の注目すべき先行事例の現地視察も併せて実施する。第二に、産業社会化/サービス空間化されて衰微している場所をいかに再生/デザインしうるかについて、ホスピタリティ経済の諸理論に学びつつ、鹿児島市(主に谷山地区)と大隅半島地域(主に南大隅町を予定)をフィールドに、活性化のプロジェクトを実施する(具体的には場所の文化を活かした出版事業の立ち上げを予定)。そのさい、場所の固有文化を理解するべく、伝統の祭りや習俗等を対象に文献調査や参与観察もおこなう。
【研究者:武田篤志】

研究テーマ香港、台湾の歴史的港湾空間の保存、再生と地域社会
コンテナハブ港湾化の国際的な競争下で大きな変容を遂げつつある東アジアの港湾都市のなかで香港、台湾を事例とし、近代を中心とした歴史的港湾空間(施設、町並み)の変化とその保存、再生に関わる行政や地域社会の対応を明らかにする。その際、清水盛光『支那社会の研究』などで指摘されてきた伝統的な中国社会の特質がどのように関わっているかについて検討をする。1年目は香港を対象とし、近代的港湾空間の変容とその保存、再生についての行政、地域社会の対応について調査する。2年目は台湾の港湾都市を対象とし、同様の課題について調査する。最後に両者の比較を通して港湾空間と行政、地域社会の伝統性、現代性の共通性、差異性をまとめる。
【研究者:森勝彦】
2.過疎・離島における地域福祉や地域振興策についての研究

研究テーマ離島の地域福祉推進と日常生活圏域での包括ケアの構築
甑島は平成の合併を経て、数千人規模の島が10万人の人口を有する地域になったが、離島であれば受けられていた様々な補助が打ち切られ、物事を決めるにも島内だけで決められなくなるなど不便さもある。このような、合併がもたらした地域への影響を踏まえ、甑島にターゲット絞った地域福祉調査、地域包括ケアシステムの構築を考える。1年目は島民へのヒアリング及びアンケート調査を実施し、結果について報告会やワークショップを開催する。その後、社会福祉協議会および住民との甑島の地域包括ケアの在り方について話し合い、最終報告書を作成し2年目の予定を確認する(社協や住民とのアクションプランをめざして)。
【研究者:高橋信行】

研究テーマ地域と学校の境界を越えた学習環境の創出とコミュニティ・リノベーションの可能性
地域と学校の境界を超えた学習環境について、前半は高校と大学を中心とした学校改革に関して動向や地域に与える影響を研究する。その後、調査対象を選別し、インビュー調査を実施する。現在、注目される取組みは、NPO法人カタリバや沖縄県の「夢実現『親の学び合い』」、大分市の「地域デザイン学校」、フィリピンのNexSeedであるが、学校改革が地域との関係を変えていくことがより顕著な事例をさらに発掘して調査をしていきたい。
【研究者:馬頭忠治】

研究テーマ過疎・離島地域における「限界集落」問題と地域農業振興策ー離島・過疎農村社会維持・存続・発展条件の解明ー
5月までに研究レビューを通じて論点を確認すると同時に、離島・甑島等を視野に再度統計分析を行い、仮説等の検証を行う。その後、南大隅町をはじめとした過疎・離島農村・集落の実態調査及びアンケート調査を行う。また離島における先進事例とされている島根県海士町での調査も予定している。2月までには補足調査、および統計分析の確認を行い、国際経済論、アジア途上国経済論なども視野に入れて離島問題の論点整理を再度行う。
【研究者:渡辺克司】

研究テーマ甑島における方言研究の成果を地域振興に活かす
- 甑島の方言を調査・分析し、その系統を調べる。また、地域での住民の方言使用の実態と方言の地域における役割を調査する。
- 甑島における方言と文化の関係を調査する
- 地域振興策としての方言を考える(観光案内図や街灯のタペストリー、カルタ製作等)
【研究者:祖慶壽子】
3.現代社会における福祉課題についての研究

研究テーマ職能団体としてなぜ機能しないのか?~あなたは介護福祉士会を知っていますか?~
介護福祉士の有資格者が増える中で、介護福祉士の職能団体として存在する鹿児島県介護福祉士会の入会率は4%にとどまっている。現場の介護福祉士が求める介護福祉士会の活動等について考察するため、先行研究のレビュー及びアンケート調査・ヒアリング調査を行う(調査対象:介護福祉士会未加入の介護福祉士 50名)。
また、鹿児島県介護福祉士会の活動実績を把握し、鹿児島県介護福祉士会と他県介護福祉士会の会員加入数及び加入率の比較ならびに他職能団体の加入数及び加入率の比較を行う。
【研究者:高橋信行・鹿児島県介護福祉士会】
4.中国社会に関する研究(清水理論の検証と発展)

清水理論を枠組みとした「家」概念の再検討は文献調査で実施される。6月締切の地域総合研究所紀要に投稿予定。夏期休暇中には、中国甘粛省で農村地域における親族組織に関する聞き取りを実施する予定である。社会調査と銘打っての調査は容易ではないので、日本から同地を訪問する使節団と合流して現地での聞き取りを実施する予定である。
【分担研究者:竹安栄子】
5.地域社会と地域振興に関する実証研究
- 地域社会の意思決定領域における女性の現状
昨年度に引き続き、鳥取県でのインタビュー調査、資料収集および昨年度発掘した鳥取県内の女性地方議員の政治活動記録の整理を行う。 - Community Based Tourismによる地域振興に関する研究
スコットランドの島嶼地域におけるCommunity Based Tourismと女性の地域社会への参画に関する現況調査。6月末にSky島調査を実施予定。 - 市民生活と観光産業の共存
世界的な観光地京都の中でも最も人気のある京都市東山区祇園地区を事例に、観光地におけるまちづくり活動や市民による景観保全運動の取組を中心とした事例調査を実施する。
【分担研究者:竹安栄子】